覚えることって本当にたくさんありますよね…せっかく覚えてもすぐに忘れてしまい、また覚え直すという無限ループに嫌気が差している方も多いのではないでしょうか。せっかくなら、定着しやすい方法で覚えたいもの。
そこで、予備校のチューターをしている私が、普段生徒にしか伝えていない「定着しやすい効率的な暗記の方法」をこっそりご紹介したいと思います。「暗記=赤シート」の固定観念にとらわれている人にこそ、大学受験から資格試験まで勉強をし続けて培ってきたノウハウをぜひ活かしてください!!
暗記の基本は「反復」と「アウトプット」
反復しなければ無駄になると思え
まずはじめに、記憶を定着させるには反復が欠かせません。つまり復習ですね。この反復作業を行わないことは、覚えた時間を無駄にしたといっていいほど愚かな行為です。覚えた日の翌日に確認し、覚えていたらその3日後にまた反復していくのです。そして、その間隔を徐々に長くしていくことがポイント。(1)翌日⇒(2)3日後⇒(3)1週間後⇒(4)1ヶ月後⇒(5)3か月後といった感じですね。
もし覚えていなかったところは、1つ前のステップに戻って反復しましょう。例えば、1週間後に忘れていたら、覚え直した日から3日後(ステップ2)にまた反復してみて、覚えていたらまた1週間後に反復していきます。残念ながら人間は忘れていく生き物です。一度で完璧に覚えられることは絶対ありません。一度で完璧に覚えようとしないことが大切です。
【19.7.14追記】一度にたくさん覚えることはできない
一度に英単語を50個覚えるなんて無謀です。というのは、人間の脳は一度に大量に覚えることはできないから。1回5個を間隔をあけて10回に分割して覚えた方がまだ効率的です。あと、「覚えなきゃ!」と思いすぎない方がいいと思うんです。テレビやSNSとかで話題になった内容って普通に覚えてますよね。覚えようと思ってなくても。
インプットで完璧にしようとしない
アウトプット作業が大切
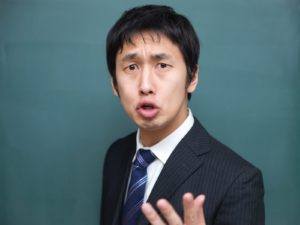
「問題を解く」「一問一答問題集をこなす」「人に教える」といったアウトプットは、非常に重要な作業です。中には、アウトプットを先にやれ(先に問題を解け)という人までいるくらいです。
正誤問題が一番よいアウトプット
一番おすすめなのが、正誤問題です。文の内容が〇か×か判断するという単純な問題ですが、短時間で済むわりに効果的です。合っていると判断するには、誤りの箇所が1つもないことを注意深く吟味する必要があるからです。
「合っているだろう」という前提で「さらっと読む」だけでは何ともないかもしれません。しかし、注意深く考えながら読んでいくと「あれ、本当にこれで合ってたか…」と自信を持てなくなる箇所が出てくるはずです。それこそ、覚えきれていないところなのです。
インプットだけでは完璧に覚えられない
インプットとアウトプットの繰り返し

なにも、100%完璧に覚えてからアウトプットを始める必要はありません。「90%くらいちゃんと覚えられたかな」と思ったらさっさとアウトプット作業を始めてしまいましょう。そして、覚えていなかったところをその都度インプットし、またアウトプットをする…の繰り返しでよいのです。
アウトプットをすることで、「覚えた気になっている」のではなく、本当に覚えているか確認できます。さらに、「うっかり見落としていた部分」や「思い違いをしていた部分」の発見ができることもポイントです。
「そのページを見れば思い出せる」ではダメ
同じテキストを何度も使っていると、テキストのページ全体を画像ファイルのように覚えてしまうことがありますが、「テキストのページを見ないと思い出せない…」状態では、残念ながら「覚えた」とはいえません。
「そのページ内にある何かしらの視覚情報がトリガーとなって、思い出すことができる」だけであって、自分で一から思い出せるレベルに到達していないからです。もちろん、何も見ずともその画像ファイルが頭の中に思い浮かんでくるレベルにまで到達していれば申し分ありませんが。
インプットは局所的、アウトプットは俯瞰的
また、テキストの暗記だけでは、局所的になりがちです。「享保の改革→徳川吉宗、寛政の改革→松平定信、天保の改革→水野忠邦」が分かっていたとしても、江戸時代の三大改革は「享保・寛政・天保」と答えられるかが問題です。前者は1対1対応ですが、後者は網羅的なものですよね。他の分野と混同していることなども確認できません。
さらに、テキストの暗記だけでは、1つのアプローチに縛られがちです。たとえ、「観阿弥・世阿弥は、能を大成した人」と覚えたとしても、「観阿弥・世阿弥はいつの時代か」といった視点を見落としているかもしれません。「テキストさえ覚えたら完璧だ」という考えは甘いのです。
最強の反復法とは何か?
自作ノートは90%覚えてから作るべし
自作ノートの呪縛にとらわれない
まず、テキストを書き写した自作ノートは、作るだけ時間の無駄です。理由はとても単純で、時間をかけて作ったことで満足して終わってしまうからです。達成感がとてもあって勉強した気になるのですが、ただの写経です。何も覚えられていません。
テキストの内容を一時的に覚えたうえで、記憶を頼りにノートを作っていくならばまだマシです。しかしながら、「写し間違い」というリスクは避けられません。
既存のテキストを活用すべし!
そもそも、英単語帳や暗記用テキストなど既存のテキストをベースに、自分好みにカスタマイズすればいい話ではないでしょうか。自作ノートを1から作る必要なんてありますか?テキストに載っていない内容があれば、関連するテキストのページに書き込んでいけばいいだけです。そのときは、写し間違いのためにも「出典」もあわせて記録しておくといいですね。
もちろん、覚えやすいテキストを購入することが暗記の近道です。定評のあるテキストは以下の条件を満たしたものが多いですね。
(1)適度に余白があって見やすいもの
(2)重要なところがどこか分かりやすいもの
(3)丸暗記するだけの内容でないもの
(4)図や表、対比、箇条書きなどで整理されたもの
自作ノートは、90%以上テキストを覚えてからにする
ただ、テキストを覚えこんできた状態に達すると、テキストをひたすらめくることが増えて大変です。このような状態になったときこそ、自作ノートの出番といえます。覚えることをリスト化してノートにまとめておけば、テキストをひたすらめくる必要がなくなりますよね。
暗記=赤シートという思い込みをやめる
「既存のテキストだと、重要な部分が赤い文字ではないから暗記しづらい!」という声をよく耳にします。中には、テキストに専用のマーカーを引いて赤シートで隠せるようにしている場合すらあります。しかしながら、私が声を大にして伝えたいことは、
「暗記=赤シート」という固定観念を捨ててください!!
ということです。「隠して覚える」という考えそのものを改めましょう。わざわざ隠さなくても、覚えているor覚えてないかは何となく分かるはずです。
鉛筆のアンダーラインで十分
覚えるときは、鉛筆や消える蛍光ペンなど簡単に消せるものでテキストの覚えたい箇所にアンダーラインを引く程度で十分です。何度も覚えられない箇所は波線や☆マークを書いたりして目立たせ、確実に覚えたと思える場所は消していきます。
こうすることで、「今まさに覚えるべきところ」「覚えているか確認すべきところ」を明確にできるので反復作業を効率化できます。赤シートの場合、覚えるべき箇所を簡単に変えられないことが難点です。
赤シートは仕上げの段階で十分
赤シートで隠せるメリットは、何といってもしっかり覚えたか確認できることでしょう。しかし、それは「暗記の仕上げの段階」で十分です。むしろ、仕上げの段階でなければ、赤シートは使わないでください。アウトプットでも確認できますし、何よりも反復に時間がかかりすぎます。暗記の基本が「反復」である以上、反復が億劫になっても困りますからね。
最強の反復法は頭の中で思い出すこと

アウトプットといっても、全範囲の問題集を解くのは大変です。そこで、頭の中で思い出す方法をぜひやってみてください。何も見ずに「享保の改革ってどんなことしたんだっけ…」などと思い出す、いわゆる「1人授業」です。友だちと問題の出し合いっこをするやつの友だちがいないバージョンですね(悲しい)。
思い出したら、すぐにテキストを見て確認します。「間違っていたところ」「思い出せなかったところ」「思い出す対象にすらならなかったところ」をチェックして、覚え直しましょう。ただ、パッと思い浮かばなくても、問題文で問われればすぐに思い出せるレベルならばあまり問題ではありません。
電車の待ち時間、満員電車の中、お風呂の中、歩いている間などのスキマ時間を有効に活用できるのでおすすめな方法です。テキストをスマホの写真で撮ったりしておけば、テキストを持参しておく必要もないですね。
まとめ
暗記で大切なことは、「反復」と「インプットとアウトプットの繰り返し」です。一回で完璧に覚えようとしてはいけませんよ。


